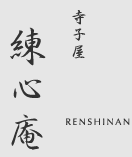2016/06/22 第2回「初歩からの仏教ワークショップ 四威儀の禅」
6月22日、花園大学の吉田叡禮先生を講師にお招きしまして第2回「初歩からの仏教ワークショップ 四威儀の禅」を行いました。
そのときの様子を参加者の大西龍心さんがFacebookでリポートしてくだいました。
ご本人の許可を頂いてここに転載させていただきます。
皆様もどうぞ講座のご感想などお寄せください。

本日の練心庵は『初歩からの仏教ワークショップ 四威儀の禅』の第2回目。
今回も前回同様に花園大学の吉田 叡禮先生をお迎えして、四威儀の禅ワークのうち「立禅」を中心に学ばせていただいた。
まず白隠禅師の「動中の工夫、静中に勝ること百千億倍す」という言葉を取り上げられたが、今回のワークの眼目はこの「工夫」の文字にあったのではないか。
坐禅というスタイルが止観(≒瞑想)に向いていることは『天台小止観』に「坐中において止観を修すとは、四威儀のなかにおいてすなわち道を学ぶことを得れども、坐を最勝となすが故に、まず坐に約してもって止観を明かさん」(坐禅のなかにおいて止観を修習するとは、行住坐臥の日常生活のなかで仏道を実践するのであるが、坐禅のなかで止観を実践するのが最もすぐれているので、まず坐禅中の止観法を説くことにする)とあるように明白なのではあろうが、日常生活の中でそうそう坐ってばかりもいられない。
まさに行住坐臥全てに「工夫」をすることは身体感覚を取り戻すことであり、今流行のマインドフルネスと相通じるものがあるような気がした。そういった流れの中で「軟蘇の法」を実践し、煉炁(れんき)、行炁(ぎょうき)を味わう。
(※このあたり詳しくは直接吉田先生にお聞きください)
お話の中で出た「行は(できるかできないかを)心配することではなく、やってみること」という言葉が印象的だったが「仏教」、「仏道」、「仏行」その関係性の一端を垣間みたような気がした。
次回も非常に楽しみである。
(記:大西龍心さん)